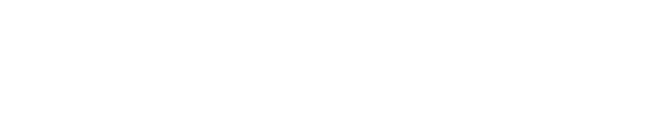要約
クールノー競争とはクールノー型寡占(企業がプレイヤー、利潤(売上と費用の差)が利得、生産量が戦略、相手の戦略と自分の戦略で自分の利得が決まるゲーム的状況)である。クールノー型寡占状況下にある二つの銀行が貨幣供給する貨幣市場で、利子率が一意に求まることをモデル(詳細後述:銀行の貨幣供給の費用が利子率であり、ただし利子率が同一の貨幣市場の需給一致で決まるモデル)で確認しながら、最終的にヴィクセルの説く自然利子率(詳細後述)について考える。
モチベーション
ヴィクセルの自然利子率。低金利にも関わらず物価上昇が起きないのはなぜだという問題意識に対して、ここで「低金利」とはどのような基準で言っているのかを考えたとき、直感的に低めに設定された銀行の貸付利子率が、自然利子率との比較では、実はまだまだ高止まりの状態にある可能性を指摘したプロポジション。前提として、貨幣市場での需給一致で決まる利子率から一時的に乖離しても需給の不一致が利子率を正常な(市場均衡の)利子率に引き戻すだろうという素朴な考え方に対して、実際には銀行の経営判断で決まる利子率で貸し付けが行われるという意味で信用経済が組織化されていると利子率の高止まりや、その逆が起きるという実態への配慮がある。
ヴィクセルが、思索の末に到達した結論は、次のようなものでした。すなわち、なるほど銀行組織が設定した利子率(ヴィクセルは、これを「貸付利子率」と呼びました)は低かったかもしれないが、それよりも投資と貯蓄の均衡をもたらす利子率(ヴィクセルの言葉では、「自然利子率」)はさらに低かったからだ。-中略-しかし、ヴィクセルは、このような理論が成り立つのは、銀行組織が介在しない「単純な信用経済」のケースのみであり、銀行組織が貸付をおこなう「組織された信用経済」では、事情が違ってくると考えました’。【出典:『入門 経済学の歴史』根井雅弘 p103-105】
二銀行のクールノー型寡占モデル
中央銀行に相当する主体が、マネーサプライMを必ず M = qa + qb となるよう決定し、そのうえで貨幣市場の均衡利子率と同じ利子率で市中銀行に貸付ると定める。そのため自然利子率と貸付利子率がそもそも一致する前提で、一致し得ることを確認するものである。なおc ≒0.45だからと言って利子率45%という意味では全くない点は注意して欲しい。
(貨幣の)逆需要関数 p = 1 – q s.t q = qa + qb
銀行Aの貸付貨幣量 qa (0≦qa≦1)
銀行Bの貸付貨幣量 qb (0≦qb≦1-qa)
利子率 c (= p)
銀行Aの費用 c*qa
銀行Bの費用 c*qb
銀行Aの利潤 πa = (-1 + qa) qa (-1 + qa + qb)
銀行Bの利潤 πb = (-1 + qb) qb (-1 + qa + qb)
銀行Aの利潤最大化 ∂πa/∂qa = 0
銀行Bの利潤最大化 ∂πb/∂qb = 0
⇔ qa = qb = (5 – √5)/10
⇒ c = p = 0.447214…
自然利子率を考える
この c を自然利子率として達成するには市中貨幣供給量Mは
M* = (5 – √5)/5
と言うことになる。ここで中央銀行が独自にマネーサプライMと公定歩合を決定し市中銀行に貸付るとしよう。このとき公定歩合が市中貸付利子率と不一致があれば市中銀行は有利なほうから貨幣を調達し始めるだろうから、均衡するとしたら公定歩合と市中貸付利子率は一致しなければならない。そのうえで自然利子率と貸付利子率が一致するとしたらマネーサプライ M = M*は明らかであるから、上述のモデルのように振る舞う中央銀行を、自然利子率と貸付利子率が一致した信用経済の均衡を考えることが話の前提であれば、そのように定義してよい。※現実の中央銀行がこのようにならない理由は多々あり割愛する。