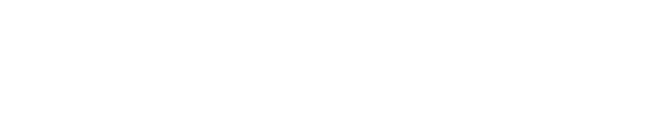スピノザ(1632~1677)は、世界のすべてのものが「神」によって在り方が規定されていると説く。投げた石ころは自由に飛んでいくように見えて、神がそのように規定した必然であると言う。同様に、人間の自由とは、神によって必然であると言う。アダム・スミス(1723~1790)の「神の見えざる手」の神が、どこまでスピノザの汎神論に接近したものであるかは定かではない。人びとの道徳感情がなせる「第三者的共感」で、悪い行いは善い行いへと修正されていく。善い行いは共感される、共感されるから行われる。悪い行いは共感されない、共感されないから修正される。これがアダム・スミスの道徳論の中枢神経だ。多くの人々の多くの具体的判断の積み重ねによって規則が形成されるという道徳論は、アダム・スミスの「自然価格(生産費用にやや利潤を上乗せした販売価格)」の概念の根幹にある。時代として、ルター(1483~1546)の職業召命観が、蓄財かつ質朴の資本主義的経営の時代を招き、やがて産業革命後の資本主義的階級社会へとマックス・ウェーバー(1864~1920)の言うように変容していく流れの中で(c.f.プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 など)、その中間期の経済史として妥当な洞察をしているのではないかと筆者は考える。ベンサム(1748~1832)の「最大多数の幸福」を経て、ミル(1806~1873)の「多様な性格や好みにあった多様な生活が個人や社会の進歩である」に至るまでの流れで、産業革命後の資本主義社会の成熟を、そう言われれば、感じ取ることができる。
カール・マルクス(1818~1883)は、資本主義的階級社会で賃金労働者は生産手段を持たず、本来の衣食住に必要な労働量を超えて労働し、資本家が超過利潤を搾取していると指摘し、賃金労働者の貧困は進行する一方だと考察した。マルクスの自由論は、スピノザ(1632~1677)の自由概念に接近していて、つまり「欲望の情動でかえって苦しむ」という考え方が基底にある。マルクスは、ある時、自分の娘のラウラとジェンニーにいろいろと質問をされた。まず「あなたの好きな徳行は。」と問われて、マルクスは「それは質朴である。」と答えている。また「あなたが一番嫌う悪徳は。」という質問には、「卑屈」と答えている。さらに好きな評語は「すべてを疑え。」だと言う。たとえば好きな評語などは学者としての学問的立場も反映されているのだろうと思われるが、彼が短絡的な弱者擁護論者でないことがよくわかる。卑屈なき方法的懐疑とは、強靭な知性そのものであり、曖昧な猜疑心とは似て非なる、つまりマルクスは知性闘争者である。
この世に仕事は三つある。「正解のわからない仕事」、「正解のある仕事」、「正解のない仕事」、この三つである。学校教育の正解率の高い者から順にこの三つを任されると考えてよい。正解がわからないからと言って、正解を教えられても覚えていられない者にはやらせられない、博打ではない、”had better”を導き出すことは更に難しい仕事である。この最も知的な仕事をドロップアウトした者は、「正解のある仕事」に流れていく。そこが、正解を参照する勉強会なのかと言えば、そうでもない。学校成績の正解率が一段階層下がるため、正しく探せば正解があるにもかかわらず、辿り着けなかったりして、あるいはそれこそ内部統制的なコミュニケーションの一環で、ディスカッションやプレゼンテーションをして、あえて自分たちで考えてやっている。優秀な者に限ってコミュニケーション不良者の烙印を押すリスクはある。
学校成績のエリートには様々な憶測が貼られているが、自制心と回避性が抜群に高い。彼らは、成績の妨げになるならば自身の飽くなき知的好奇心も制御できる。学校成績のよい者は、教科書の内容をしばしば超えて独学をしたくなるものだが、そこに自制心が働く。誤解してほしくないのは彼らは成績を「エリート通行証」だと根っから割り切って殺伐としている、わけでもなく、そのようにしているのである。本当は興味関心に従って突き進んでいきたいが、そのようなときめきを悔しがりながら諦めているのである。回避性とは、集団を維持するため他者との衝突を避ける能力である。たとえば猿山のサルをエレベータに乗せたTV番組が昔あったが、ものの数秒でパニックを起こしてしまった。サルはエレベータも乗れない。逆に知的な生き物であるほど、集団のための回避性が高く、エリートなどその典型だ。能力として、おとなしいのである。個人の能力が高くなるにつれて自由奔放では他者と衝突するリスクも高くなる、だから、である。そして自制心とは回避性と一体である。
これは批判だが、後世教科書に載るような人物が貧困を遠望しても一人ひとりは絶対に見えてこない。「すべてを疑え。」とは断じて思わないし、むしろ信用に足るものにすがりつけとさえ思う。ニーチェ(1844~1900)は、「弱者のルサンチマンとキリスト教との憐みの対話」という考え方で、当時の、貧困と宗教が結びつく様子を情念的なものと嫌っていた。筆者とて、もちろん神を拝めなどと言いたいのではないが、自分なりに正しいと思った考え方から一歩も動けなくなるのが貧困である。低層はもっぱら選択肢をマネジメントできないのである、能力も正解する、正解しない以前の低いものであるし、彼らの集団もふとしたはずみで台無しになる。彼らにとって信仰とは合理的なのである。