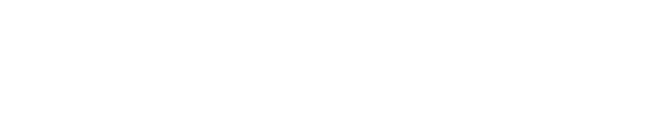しおりとつくしは、この夏休みによく遊んだ。時には友達五、六人で、自転車で川沿いの公園に行ったり、つくしの住む団地の広場で遊んだりもした。お互いが宿題を手伝った日もあったし、達哉が、市民プールに併設された卓球場に二人を連れて行く日もあった。
しおりは、つくしに会えば、卓球とは友情の架け橋だと思った。達哉との親子の絆で始まったものだが、卓球は人と出会う喜びを与えてくれる。
しおりの、卓球が上達したい気持ちと、皆で仲良く卓球をしていたい気持ちは、同じくらいの大きさだった。静香のように身体を鍛えて、誰にも負けないくらい強くなりたいと思う日もあったし、奥井に勝ちたいと思う日もあった。それとは対照的に、達哉、つくしや卓球教室の友達とピンポン玉の音を聴いていれば幸せな日もあった。
ある日の晩、達哉は、隣の市で小学生以下の大会があると言い出した。観戦に行かないかとしおりを誘った。小学三年生はカブだから、三、四年生と対戦するよ、神道静香みたいな子が来るよと言って。
しおりは、
「行きたい!」
と言った。
清恵と、祖母・林子も行くと言う。林子は、お婆ちゃんが払うから、お昼はレストランに行こうね、としおりに言う。しおりは、嬉しさのあまり、つくしも呼ぼうと言う。
達哉は、幾らか世間知があったから、入会して間もないのに大会の見学に連れ回したらよくないのではないかと、清恵に言う。
清恵は、早速、反町家に電話をした。
電話口の大悟は、ウチはお盆休みが無いと言いつつ、それでいて嬉しそうに、つくしを一日村木家に預けると言った。お盆休みの土曜日に隣市で開かれる「JETS杯」という県内オープンに村木家とつくしは観戦に行くことが決まった。
JETS杯当日は晴れた。朝早くに出発し、会場の体育館に早めに着いて涼んでいようと決め、団地のバス停に集合した。いつもとは逆方向のバスで沿線の駅まで行く。
バスで隣同士になったしおりとつくしは、卓球の大会を観に行くのだから、卓球の話題をしようかなと思うと、自然と会話が弾んだ。しおりは、声を弾ませて明るいつくしと、逆方向に走るバスの車窓から見える風景に、ワクワクする気持ちを募らせた。
沿線の駅から二駅ほど行く。林子は高齢だが、駅からの道を達者に歩いた。つくしは村木家の人々が全く苦手ではない様子で、夏休みにちょっとした思い出が出来そうだと喜んだ。
会場の市民会館に着くと「観戦の方」と書かれた立て看板が親切に立ててあり、それに従い、体育館の観覧席に移動した。受付の選手達、彼らの行列を尻目に二階へ向かった。
二階の観覧席から見下ろす、何列も横に並んだ卓球台と、縦に仕切るための青いパーテーションで埋め尽くされた体育館の一階。道中の明るさとは打って変わって、しおりは、開会式前のどんよりとした空気を、どこか恐ろしいと感じ、ゴクリと唾を飲んだ。これから、静香のような子ども達が一同に会して、あのような芸当で卓球をするのかと思った。
つくしは、
「うわあ!体育館がこんな風になっているのは見たことがないな!」
とはしゃいだ。
しおりの心境は、つくしの反応と対照的だった。ここで強い子と弱い子の決着がつくのだと思うと、奥井卓球教室では味わえない緊張感が湧いた。その為に大勢が集まる。いつか達哉が言っていた、奥井としおりの間に沢山の子がいるよという言葉が思い出された。確かに沢山の子がいそうだと実感を伴った。
「しおり。そう言えば、東洋卓球クラブに知り合いがいるんじゃなかったのか?」
「来ているかな?」
「挨拶しに行こう」
「話しかけちゃ悪いよ」
「卓球仲間同士、話しかけちゃ悪いなんて無いだろう。探して挨拶しよう」
達哉は、
「これから開会式前の全体練習だろう。観客は試合会場のエリアには入れないし」
と言った。
それを聞いたつくしが、
「しおり!さては試合に出られるのが羨ましいんだろう!」
と言ってからかった。
しおりは、ギクッとした、実際は怖気づいていたからだ。
「そうだよ!」
しおりは少し虚勢を張って、そう言った。
それから午前中、村木家の一行は、小学三、四年生の部(カブ)の予選リーグを見た。四名の総当たり戦で一位が通過する。カブと一緒に、一、二年生の部(バンビ)と五、六年生の部(ホープス)も同時に行われた。
カブ女子は六十名規模だった。
会場に静香はいた。予選が始まると、しおりはすぐに見つけたのだ。動きのキレが抜群だ。静香は県内オープンでも一際目を引く実力者だったではないか。東洋卓球クラブのユニフォームを着て、躍動する静香の身体。
つくしは、あの子とかしおりの方が強そうだけどな、と言う。静香の対戦相手の事だ。達哉は、端から見ていると案外弱そうに見えるのも卓球の面白さだよと教えた。
静香の相手選手がバックハンドで下回転をかけたのを見た瞬間、達哉は、
「今のとか。あれであんな打球速度になるのは相当練習しないと出来ない。なんでもいいなら誰でも打てる速さだけどね」
と言った。
つくしは、
「そっか!奥が深いんですね!」
と言った。
しおりは、それを対角線に順回転のスマッシュで返球する静香を見て、ようやく何かを掴みかけていた。下回転に対してはつっつきで返すのが易しい。それをあえてスマッシュで打ち返すのは卓越した芸当だ。順回転を順回転で返す時と、下回転を順回転で返す時は必要な摩擦が異なるから、飛んできたピンポン玉がいずれの回転なのか瞬時に判断しなければならないし、飛び交う球が速ければ速いほど「予測」というプロセスを余儀なくされる。
しおりは、胸が熱くなった。達哉の勧めで始めた卓球は、奥が深く、見ていても情熱的になれる。
達哉は、
「あと相手の子が強すぎる。あれが神道静香だ」
と言った。
しばらく見ていると、達哉は「なるほどな」と頷いて、大人と子どもでは差があって当然だが、カブ女子の予選リーグなら俺でも通過できると言った。カブ女子も強い子はうんと強いが、全体の競技レベルは達哉より強ければ県内オープンの予選は通過するだろうとアドバイスした。
しおりは、それを聞いて益々奮い立つのだった。
清恵は、
「でも、あっちにも神道さんと同じくらい強い子がいるわね」
と言って、別のエリアを指さした。しおりは、凄いね、お母さんよく見つけるね、と驚いた。その子は確かに機敏に、ミスなく打っていた。
予選リーグの後は、昼休憩を挟んで決勝トーナメントが始まる。達哉が、昼は市民会館のカフェで食べようと言い、林子も、レストランがある建物で良かったね、外は暑いものねと言った。選手達は、予選リーグを終えた者から順次、昼休憩だった。
しおりは、静香が予選リーグをぶっちぎりで通過して、体育館から退場するのを見ると、今度こそ挨拶しようと思った。一度対戦しただけの自分を覚えているか、どうかは無頓着に、試合観戦をして高ぶった感情のままに、静香に応援の言葉をかけたくなった。
体育館の外のテラスで、昼休憩中の東洋卓球クラブの選手達の集団が座っていた。しおりは静香を見つけると、思い切って声をかけた。
「神道さん!こんにちは!」
静香は、小さく頷くと、すくっと立ち上がって、しおりとつくしの方へ歩いて来た。
「朝、入口で見かけた時は、出場選手かと思ったじゃないか」
「今日は観に来たの!神道さん!凄く強いね!もう一人、強そうな子がいたよ!」
静香は少し悩んでから、
「白石かな。白石瑠花。バンビ(一、二年生の部)で有名だった。あいつも三年生だよ」
と言って苦笑いした。
つくしは、
「強いと楽しいのか?」
と不敵に聞いた。
静香は、また少し悩んでから、あえてしおりの方を向いた。そして、しおりの四肢や体幹をマジマジと見てから、
「村木さん。私は前に、順回転を極めろって言ったけれど。技は、それを扱うためにこしらえた心と身体の産物だ」
と言って、フッと目を落とした。その次の瞬間、つくしの方を向いて、
「貴方は?」
と聞いた。
「反町だ。始めたばっか」
「楽しさも道だ。私は違う」
「そっか。なんか邪魔したな」
「反町さんも。楽しいからどうのって感じじゃ全然ないね」
「はあ?」
「そんな感じがする」
「そうか?」
静香は、フッと笑って、戻って行った。
しおりは、去って行く静香を名残惜しんだ。もう少しお話したかった。もしかすると静香は、楽しいという感情を捨ててでも、どこまでも強さを極めるのだろうか。
しおりは、昼食のカフェで、なんとなく静香が食べていたおにぎりを思い出した。食事を終えても、胸の中に残存する何かがあった。選手として大会に出たいという気持ちが、まるで膨れ上がっているように。つくしの顔をチラッと見ると、どこかあっけらかんとしたつくしは、武士みたいな人だったなと静香を語った。
しおりは、静香の言っていた白石瑠花という選手が、あの強かったもう一人の子かなと思った。実際、的中していた。昼食を終え、カフェを出ると、いつの間にかメディア関係者のカメラマンらと思しき人達が到着していた。件の子を取材しながら、史上最年少プロに意欲はありますかとか、バンビの頃と比べて大会の雰囲気はどうですかとか、そんな質問をしていた。今、メディアが注目する将来有望な天才卓球少女が、件の白石瑠花だった。
しおりは、強くなって、多くの人と出会えば、楽しいのではないかと思った。たとえば今、目の前で脚光を浴びる白石瑠花と試合で渡り合って。そう考えると静香の言い残した言葉は異様に意味深だった。楽しさも道とは、そういう意味なのか、であれば強さを極めるとは何か、静香は自分達と出会ってどう感じているのか。
そう思った矢先だった。とても鈍い声がして、しおりの耳に届いた。
「死ね」
しおりは、声の主が自分の近くにいたから、直ぐにわかった。つくしも、なんだ?という表情。声の主は白石瑠花をギョロリと睨んでいた。しおりは、
「どうしたの?」
と呼び止めた。
声の主は、無視して去って行った。微妙な後味を残して昼休憩は終わった。
昼休憩後の決勝トーナメントは、思いのほか展開が早かった。三セットマッチで、負けたら終わりの勝負は、カブの準々決勝まであっさりと終わって。静香と白石瑠花が順当に勝ち進んだ。勝てば決勝で当たる二人。しかしメディア関係者らは相変わらず白石瑠花に注目したきり、静香にはあまり関心が無さそうだった。
しおりは、胸がチクりとした気持ちで、静香が脚光を浴びたらいいのにと思った。カブ女子の準決勝が始まると、シャッター音が鳴り響いた。しおりは、メディアの注目しない静香を応援しようと思った。せっかくあんなに鍛えたのだから。見ている自分も胸が熱くなって来たのだから。静香には勝って欲しい。
それから五分程が経過した頃だった。事件はもう一つの準決勝で起きたのだ。しおりの純粋な想いとは対照的に、体育館はどよめきが支配し、バンビやホープスの試合が一時中断するほどの音になった。
「セカンドサーブ、ナイン、テン、マッチポイント(九対十)」
しおりが、そちらに目をやると白石瑠花がサーブを打とうとしていた。九点は白石瑠花。一点リードでマッチポイントの相手は、越谷スティーラーズの小学三年生、雲越たままという子だった。先程の、不気味な声の主ではないか。
達哉が、
「こっち側の準決勝をずっと見ていたけれど、レシーブがヤバい」
と言って、気楽に見ていられるはずの立場なのに深刻な表情を浮かべていた。
「レシーブがヤバいってどういう意味?」
次の瞬間だった、白石瑠花のサーブが放たれた。
「どんな回転かけてもダメ。必ずこれでやられる」
雲越たままは、サーブを台と同じ高さで打ち返した。しおりの得意技でもある、ループドライブで。しおりも、一瞬自分と同じ技を使って組み立てる選手だと思ったが、ピンポン玉はネットを越えて、バウンドすると同時に、ほとんど弾まず台上を転がった。
「セット、ナイン、イレブン(九対十一)、雲越さん」
雲越たままのループドライブは弾まないループドライブだった。
「白石さん、自分のレシーブで一回もミスれない。ヤバい」
達哉がそう言うと、静香の試合をチラッと見た。
「こっちの試合は、神道さんが一歩リードだね」
「お父さん、私は静香ちゃんに勝って欲しい」
試合は、静香の優勢ながら僅差だった。対戦相手は、ドロップショットを効果的に用いて、攻撃力の高い静香を翻弄して粘っていた。クレバーなタイプだった。
達哉は、頷くと、
「俺はトイレに行く」
と言って、観覧席から退出した。
メディア関係者の困惑は際立っていた。予選リーグで見た時は白石瑠花クラスに「同じ遊び」が通用するとは思わなかった、不覚だったと口にしていた。確かにネット際の攻防を選べば、弾まないループドライブを封じられると誰しもが思う。しかし雲越たままは、何をやってもレシーブは弾まないループドライブだった。
白石瑠花は、ストレート負けした。報道陣の期待とは真逆の結果にショックが大きく、その後の三位決定戦も棄権した。
決勝進出の静香へ、東洋卓球クラブの監督とコーチは、何か熱心にアドバイスしている様子だった。しおりは、静香に何か助言できないかと思ったが、全くそのようなレベルに無く、ただ観覧席から頑張れと念力を飛ばすことしかできない。
決勝戦で、静香は、雲越たままの弾まないループドライブに歯が立たず惨敗。そしてこの大会は終わった。静香は、様々な技を試したが、雲越たままのレシーブは揺るがなかった。負けても静香は、強かな表情だったが。
決勝戦の間に、離席から戻って来た達哉は、清恵に何かを話している様子だった。
表彰式は試合後すぐに執り行われた。
しおりは、準優勝の賞状を受け取る為に試合会場で佇む静香の背中を見て、つくしに、
「技は、支える心と身体をこしらえた者の持ち物だって言ったよね?」
と、不安気な声で尋ねた。
つくしは、
「そうだな。雲越もそうなんだろう」
と言ったが、冷たい様子はなかった。しおりに、心配するなと言葉を添えた。
それでもしおりは、静香は負けてどう思ったのか、分からなかった。もしかしたら試合中の静香も、蔑む言葉を浴びせられたのだろうか。白石瑠花は「死ね」と言われた。しおりは、静香が心配になり、
「静香ちゃんに、準優勝おめでとうって言って来る!おめでとうって言ってあげる!」
と言った。今にも観覧席の階段を駆け下りて、直接試合会場に走り出しそうなしおり。
達哉は、
「しおりに見せたい人がいる」
と言った。
しおりは、突然、なんだろうと思い、達哉を見ると、達哉は、試合会場にいる一人の女の子を指さした。
「藤間美香。三位入賞だ」
清恵は、
「本当にあれが藤間さんの娘なのね?」
と、細い声で達哉に確認した。
「そうだ!」
達哉は、しおりに、いつかと言わず大会に出てくれ、と力強い口調で言った。達哉は、今日恐らくは件の藤間という人物と、遭遇していたと思われた。
藤間美香は、薄っすらと笑い、三位ながら自信に満ち溢れた顔をしているように見えた。大健闘という事なのだろうか。学年も一緒だった。
しおりは、ここで自分自身の戦いを意識し、心がゆっくりと切り替わった。そして、静香の準優勝を、友達の目線で讃える気持ちが穏やかになった。
この日を境に、しおりとつくしは、まず身体をうんと鍛えるようになった。卓球は毎日でもやりたかったが、達哉が卓球場に連れて行ってくれる日しか、練習できないのが少し歯がゆかった。そんな二人の夏休みには、もう一つ大きな出来事が待っていた