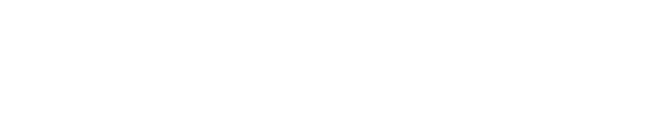それは夏休み最後の土曜日に起きたのだ。宿題を片付けたしおりとつくしは、奥井卓球教室にいた。
あっ!
くそっ!
このっ!
はっはっはっは!
二人は試合のような、ラリーのような、卓球台で向かい合って技を確認し合う事を、延々と続けていた。冗談のような笑みの零れる時を過ごしていた。
つくしは、
「やっぱり卓球台があるといいな!基礎体力トレーニングやフォームチェックをしていても卓球台で打たないと感覚が身につかない」
と言う。
しおりは、
「何が分かって来たの?」
と聞いた。
「打とうとする球がネットより高いか低いか、高い時にどれくらい高いか、瞬間でわかるようになった」
「低い時のつっつきが安定したのは、そのおかげだね」
「おう!ステップも自然と刻むようになったし!早くしおりに追いつくぞ!」
しおりは、静香に言われた通り、順回転をマスターしようと心掛けて来た。それが、相方のつくしの上達に繋がっていた。回転が素直なぶん、つくしは基本が身に着いた。
つくしが、ダンと踏み込んでスマッシュを打つと、ピンポン球が台上で弾けて鋭く飛んで行った。
「今のは二十センチくらい高い」
「ムカツク!」
しおりが奇声を上げると、奥井が、いやいや、しおりちゃんも腰でスイングするようになったし、身体を鍛えたのが無理なく技に繋がっているよ、と言う。
奥井は、しおりに代わって卓球台に向かって立つと、
「奥井サーブ!」
と言って、つくしに変則サーブをお見舞いした。ピンポン玉はネットを越えると、弾みながらキュルキュルとサイドに逃げて行った。
「今日は短く打たれた時のレシーブを伝授します」
奥井も、しおりとつくしを穏やかに特別扱いするようになった。二人は仲間からも「超強い」と認知されて、いくらか時間が経っていた。
そして事件は二人の帰り道で起きた。村木家の達哉と清恵は、つくしが相方になってからは、しおりの送り迎えをしなかった。
つくしは、身体を鍛える一環と言って、三キロメートル程の道をジョギングで帰るぞと、しおりを誘った。しおりは、そうだね、と言った。走れるくらいじゃないと静香のようになれないかなと思った。
つくしは、走って帰る道を把握していた。二人で猛暑の中を、えっほ、えっほと駆ける。雑木林を抜けて、大きな公園を横切って、坂を下れば市営団地だ。
しおりは、アスファルトを踏みしめる足と膝の感覚を覚え、必要なトレーニングだと直感で思った。これから徐々に涼しくなるのだから、自主練にジョギングを取り入れようと意識を持った。
しかし暑い。
二人は体力を消耗しながら、暑い、暑いねと口にした。
そして雑木林を抜けて、大きな公園を横切ろうとした時だった。
中学生の集団に突然、
「待てや!」
と怒鳴られた。
つくしは、そのまま走り去ろうとしたが、しおりが驚いて足を止めてしまった。すると中学生四人組が小走りに寄って来て、二人はあっという間に囲まれてしまった。背が、壁のように高い。囲まれてからは、足がすくんでしまった。
四人の中に、女子が一人いた。女子は猫なで声で、
「この辺の子?ねえこの辺に住んでいるの?」
と二人に話しかけた。
しおりは、引きつったように笑った。怖いと思ったが、声が、猫なで声で、親し気と言えば親し気なのだ。無言の男三人は、恐怖以外の何物でもないが。
つくしは、
「何も持っていません」
と言う。
女子は、
「みして?」
と相変わらずの奇妙な声で言う。そして容赦なく鞄を開けられ、二人はバス代計四百円を暴かれてしまった。
「あんじゃん」
男三人も言葉を発し始めた。しおりは、場数を踏んでそうなつくしを恐る恐る見るが、つくしこそしおりを見ていた。緊張という言葉では足りない感覚が背筋を襲う。カツアゲの四人は、明らかに弱い二人を取り囲んで、怖がらせて遊んでいる。しおりには、この後どうなるか分からない恐怖が、心を支配していた。猛暑である事などとっくに忘れてしまった。どうやったらこの状況から生還できるか、見当もつかなかった。
「じゃあ鞄についているアクリルキーホルダーも貰っちゃおうかな」
と誰かが口にした時だった。
女子が、
「あ!」
と叫んだ。
女子は、鞄の中身に、驚き、目を丸くしてしおりを見た。
「待って!卓球のラケットがある!」
しおりは、直感で卓球のラケットを奪われるのかと思った。それは許さんという気持ちが湧いた。ただ恐怖が、遥かに他の感情を凌駕していて、やめてくださいと言うのが精いっぱいだった。
女子は、しおりの顔を見ると、
「卓球の子かな?」
と尋ねて来た。
「はいそうです」
女子は、他の面子に向かって、
「卓球の子だ。マーサン、この子、卓球の子だった。シンジも、この子、卓球の子」
と言い出した。
「スプレーもある。これ手入れするやつでしょ?」
「はいそうです」
「卓球の子だね」
「はいそうです」
女子は、また奇妙な猫なで声になって、
「ウチについてきたら、お金返してあげるから、来て。ほら、返してもらわないと親に怒られちゃう」
と言った。
一人がマーサンで、一人がシンジというらしいが、そんな事はどうでもよかった。男三人が、しおりとつくしを囲んでトボトボと歩きながら、女子の向かう先に二人を連行した。女子は、時折、振り返って微笑んだ。何か意味があるのだろうか。しおりには、夏の暑さが、少しは蘇ったかもしれない感覚があった。帰り道と方向が一緒だったからかもしれなかった。坂を下っていく。
向かった先は、女子の家だった。公園から歩いて五百メートル程の所にあった。表札に「灰沢」と書いてあった。なぜ、自宅に案内されたのか分からなかったが、しおりは、テレビで報道される怖いニュースを思い出して、いよいよ観念してしまった。ここで何をされるのだろう。
その時だった、男三人は帰らされた。女子は、またねと言って、男三人を帰らせたのだ。マーサンと思しき男が、「ユウコ、そしたらまた明日」と言って、心なしか面白くなさそうに引き上げて行った。女子は、ユウコというのか。
二人が連れて来られたのは、二階の子ども部屋だった。
ユウコは、
「鬼里火ちゃん、お友達だよ!」
と急に明るい声になって、中にいた女の子を呼んだ。しおりは、そんな言葉のあやよりもむしろ、部屋の広さと、そこにある卓球台に声を発さず驚いた。
「お友達連れて来たよ!卓球やろうね!」
ユウコは、小学三年生の妹と卓球台で遊ぶよう、しおりとつくしに求めた。二人は声を揃えて、卓球をすればいいのですか、と言った。
鬼里火は、無言でペンホルダーのラケットを右手で握ると、卓球台に向かって仁王立ちした。卓球台は部屋の中央ではなく、片側のエッジが壁に異様に近かった。その狭い方のスペースに、鬼里火は突っ立っていた。
しおりは、勝てばいいのか、負ければいいのか、わからないと思ったが、ユウコは、また猫なで声で、遊んであげて、と言う。
鬼里火は、
「宜しくお願いします」
と礼儀正しく、挨拶をする。
突然、つくしが思い出して、
「灰沢って、私が幼稚園の頃に傷害致死で逮捕された家だ!」
と言った。
ユウコは、若干ひるんだ様子で、
「うん。お父さんは今、刑務所だね。近所で有名になっちゃったね。学校に行けるはずないでしょ。鬼里火ちゃん、学校行けていないの。遊んであげて欲しいの」
と言った。
灰沢は、かつてこの界隈を震撼させた傷害致死事件の犯人宅だった。父親が知人男性を殺害した。裁判で殺人から減軽されて懲役八年。鬼里火は、書類上は同じ小学校に通っている不登校児童だ。ユウコも、小学校の途中から不登校児童で、中学には通っていない。真実を言えば、灰沢家は元は被害者側で、母親は、その知人男性から暴行を受けた、事件の直接の原因だった、そして判決後に自殺していた。
しおりは、
「卓球が好きなの?」
と聞いた。
鬼里火は、
「お父さんが帰って来るのを待っているの」
と、難解な事を言った。
しおりは、そんなに卓球が好きなのかと思ったので、
「じゃあ!今日から友達になってあげる!勝っても負けても友達!」
と言って、鬼里火と試合を始めた。鬼里火に、表情はなかったが。
それから、しおりとつくしは、交代で鬼里火の相手をしたが、鬼里火は強い。まずブロックと呼ばれる技術が徹底していて、しおりのドライブも、つくしのスマッシュも、構えたラケットで弾き返す。強く打てば打つほど、強い打球が跳ね返ってくる。その際、クロス打ちに対してストレート、ストレートに対しては鋭い角度を狙うのだ。全く隙が無い。
つくしは、なんで鬼里火の後ろのスペースがほとんどないのかと聞いた。おかげで異様にテンポが速い。鬼里火は、要らない、とだけ言って、真っ当に返答をしない。
しおりは、初めて見るタイプの相手だと思ったし、ブロックでドライブを弾き返される度に、鬼里火の後ろの壁に打ち込んでいる錯覚を覚えた。
しおりは、満を持してループドライブを試した。小さく山なりの、ネット際に落ちるピンポン玉。JETS杯優勝の雲越たままは、このバウンドが一切弾まないが、しおりはまだその域に達していない。
次の瞬間、ピンポン玉の正面で小さく飛び跳ねた鬼里火は、バウンドの頂点を狙い、右脇の下から右肩にラケットを振り上げてバックスマッシュを叩き込んだ。
技も多い鬼里火。しおりは、多彩な技以上にテンポの速さに戸惑い、中々自分の卓球をやらせて貰えない。しおりは前後左右に揺さぶられるが、毘沙門天のような鬼里火は移動が少ない。
つくしは、なるべくロングを狙った。鬼里火はラケットを水平に待ち構えて、手首の回転で弾き返した。これはチキータと呼ばれる技術だ。何度やっても、まるでチキータの練習のように正確に打ち返されてしまう。
鬼里火の戦い方は、卓球で前陣速攻と呼ばれるものだ。
やがて、疲れてへとへとになった二人に、ユウコは、
「お友達をやってくれてありがとう」
と言って、強奪した四百円を返還した。
「じゃあ鬼里火ちゃん。後はお姉ちゃんと遊ぼう」
ユウコはそう言うと、俯いた顔で自分のペンホルダーのラケットを取り出した。姉妹で毎日打ち合ったのだろうかと思わせる、使い込んだラケットだ。
しおりは、
「待ってください!」
と言った。
ユウコは目を丸くして、キョトンとした。
「友達をやってあげたのではなくて、友達になりました。卓球仲間です」
今度は鬼里火がキョトンとした。
「無理矢理、連れて来られたんじゃないの?」
「無理矢理だったけど、友達になるって決めたんだよ」
しおりは、ユウコの態度に業を煮やして、
「鬼里火ちゃんが友達になってくれるまで卓球をします」
と言って、ユウコを押しのけてシェイクハンドのラケットを構えた。そしてまた壮絶な打ち合いが始まった。しおりは、鬼里火の前陣速攻から技を吸収した。つくしも、負けていられないと言って、加わった。
月が出て夜半に帰宅すると、しおりも、つくしも、心配した親に顛末を伝えた。親達は不思議がっていたが、二人は鬼里火を友達と言い張った。達哉は、友達が出来たのならよかったと言った。大悟も、俺は灰沢に関わりたくない、友達じゃ仕方が無いと言った。ただしジョギングは、家の近所で済ませるようにと言われた。
しおりとつくしは、灰沢家に遊びに行くようになった。夏休みが終わり九月になっても、秘密の友達を交えて卓球をした。優子も、妹の友達になった二人を歓迎した。